- ARTICLES
- 文化人類学的視点で語る「部屋から、遠くへ」 ━前編━ 松村圭一郎×阿部航太 “街中のアートに触れ、その深層に思い馳せる”
CROSSTALK
2022.02.04
文化人類学的視点で語る「部屋から、遠くへ」 ━前編━ 松村圭一郎×阿部航太 “街中のアートに触れ、その深層に思い馳せる”
Illustration / Fuyuki Kanai
Edit / Eisuke Onda
「部屋から、遠くへ」。しかし、世界的なパンデミックに見舞われ移動を制限されたことで、私たちの「遠く」の概念は物理的にも、精神的にも変わったはずだ。
ある人は家の近所を散策するようになり、これまで気がつかなかった街の彫像から、遠い過去の人物に思いを馳せたかもしれない。またある人は、家の中にアートを飾るようになり、作品から遠くの風景を感じとることで充実した時間を過ごしたかもしれない。
目まぐるしく社会は変化し、市井の人々の価値観や暮らしも変化していく。そんな中、「アート」を鑑賞する、あるいは表現することは、どのような意味をもたらすのか。そのヒントを、文化人類学を専攻する二人の対話に求めることにした。
一人目はエチオピアのフィールドワークを行う松村圭一郎さん、もう一人はデザイナーでもあり、ブラジルのストリートアートを調査する阿部航太さん。
前編では、コロナ禍を経験した約2年間の暮らしについてと、阿部さん手掛けたドキュメンタリー映画『街は誰のもの?』に映し出されたブラジルの人々の、当たり前にアートがある暮らしについてのお話をお届けします。
『収奪された大地〈新装版〉――ラテンアメリカ五百年』著/E・ガレアーノ、訳/大久保光夫
ウルグアイ出身のジャーナリストのE・ガレアーノによる欧米先進国による収奪という視点で書くラテンアメリカ史。藤原書房/5,280円
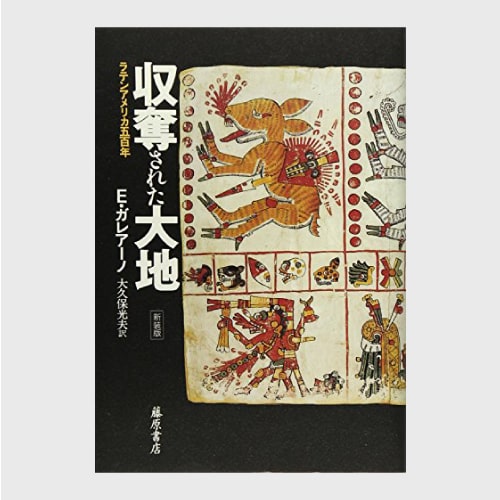
コロナ以降の「遠く」と「近く」
――今回の特集テーマは「部屋から、遠くへ」です。これはもちろん2020年より続くコロナ禍を意識したものですが、取材日の2021年12月24日時点では不透明なままとはいえ、ようやく長く続いた外出自粛が緩やかに解けつつあります。まずお二人は今日のそうしたムードをどう感じていますか?
阿部航太:僕から話をすると、このままコロナ禍が終わってくれたらという期待はすごくあります。一方で期待してはいけないと感じている自分もいる。それが正直なところです。この2年間、特に海外に行けないということが、別に気楽に海外に行けるお金も暇もあるわけではないにも関わらず、苦痛でした。「行かない」と「行けない」のあいだにこんなにも差があるものかとひしひし感じたんです。今後どうなるかは分かりませんが、もし再び海外に行きやすくなる日が来たら、それができるということの貴重さをあらためて感じることになるだろうなと思います。
ただ一方で、コロナが収束してもまた元の生活に戻るという風にはならないとも思うんです。コロナ禍においてこうしたリモート会議(この取材はZOOMで行われた)のようなものが一般化しましたよね。すると、わざわざ対面で打ち合わせをしようという時、ちょっとスイッチを入れる必要が生まれてくるんです。「よし」と意思を立てないと対面で人と会うことさえ達成しづらくなっている。だから今後は「外に出る」「遠くへ行く」という行為が以前より意思の伴った行為になっていくだろうなと思ってます。
松村圭一郎:僕は岡山県に暮らしているというのも関係しているかもしれませんが、この2年の間もちょくちょく外には出かけていたんです。もちろん遠方や海外には行けていないんですけど、岡山県内の旅行とかは割とたくさんしました。家族で貸しコテージに泊まったり、海水浴に出かけたり、寂れた遊園地に遊びに行ったり。実際、そういう場所は混んでもいないし、接触も多くないんですよね。だから「部屋から、遠くへ」という時の「遠く」を何も物理的な距離ばかりを意味するものとして捉える必要はないのかなと思います。近場でもよく知らない、わざわざ行くことのなかった場所ってたくさんあって、そういう場所にあえて足を運んでみると意外と面白かったりするじゃないですか。そうした「近く」の未知なものを再発見していくことも「遠く」へ向かうことなのかもしれないと思いますね。
阿部:たしかにコロナ禍のあいだに自宅周辺の解像度が上がった気がします。家の近所をなんとなく歩くことが増えましたし。遠くには出かけられないからコンビニに行くのも遠回りしてみたり、通ったことがない道を歩いてみることも増えました。
松村:そうそう、やっぱり運動不足にもなりますからね(笑)。
――コロナ禍によってあらためて「移動ができる」ということのありがたさに気付かされたという人は少なくないように思います。一方、コロナ禍以前を思い出してみると、人や物や資本が国境を越えて高速度で移動する、いわゆるグローバリゼーションによって生じた問題が様々に明るみになっていた時期でもあったようにも感じます。そんな中、開かれていることこそが素晴らしく、閉じていることは悪しきことだといった見方に、多くの人々が疑問を持ち始めていた。今後、コロナ禍が緩やかに落ち着いていき、再び世界が開かれていくと仮定して、私たちはただ元の暮らしへと戻っていくだけで良いのか、お二人はどうお考えでしょうか?
阿部:正直なところ、僕はグローバリゼーションの悪いところをあまり真剣に考えてこなかった人間だったんです。ただ、ブラジルに行くにあたってラテンアメリカの歴史を知りたいと思い、ある一冊の本を読みました。それは『収奪された大地』(著・E・ガレアーノ)という本で、そこにはラテンアメリカという土地の歴史が先進諸国からの搾取と収奪という観点から緻密に書かれていたんです。いかにラテンアメリカが先進諸国の大企業から資源を収奪されてきたか。知らなかったことが克明に描かれていて、読んでいてものすごいショックでしたね。もちろん、その先進諸国には日本も確実に入っているわけです。
それ以前は「閉じる」というとすごい保守的なイメージがあって、「開かれている」ことに疑問を持つだけで右傾化だと捉えてしまうようなところがあったんですが、全然そんなことなかった。たとえばパラグアイのような小国は外部からの資本主義の圧力に対してなるべく国を閉じることで対抗していこうとした歴史を持っています。でも、結局は資本主義諸国の政略に巻き込まれるかたちでそのシステムは破壊されてしまいました。実際、そうした歴史からの影響を中南米の国をまわっていると肌で感じることもあり、そこからグローバリゼーションの怖さのようなものを感じるようになりましたね。
『菌の声を聴け タルマーリーのクレイジーで豊かな実践と提案』著/渡邉格、渡邉麻里子
パンとクラフトビールの製造過程で長年“菌”と向き合ってきた渡邊格、麻里子が未来の共生社会の築き方を綴った一冊。ミシマ社/5,280円
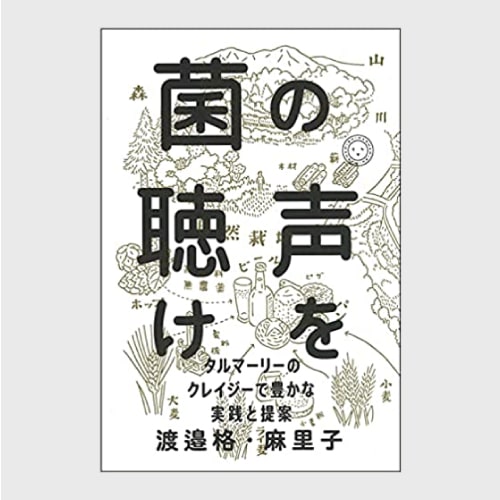
松村:この2年で、これまであんまり想像することができなかったグローバリゼーションとは異なる可能性が可視化されたと思うんですよ。目に見えるところでは、飛行機の本数が減ったり、工場の操業が停まったりしたことで大気が綺麗になったという話もありましたね。天然の麹菌を森で採取してパンを作っている<タルマーリー>の渡邉格さんが『菌の声を聴け』(ミシマ社)に書いていましたが、2020年の夏はカビが混じらないきれいな麹菌が採取できたそうです。そういう話を聞くと、僕たちは今まで無駄に色々と動きまわってきたのかもしれないと思ってしまいますよね。なんでみんなこんなにあくせく移動していたのか、それは強迫観念のようなものだったんじゃないだろうか、と。
さっきの話もそうですが、別にコロナが明けたから遠くに行けばいいというものでもないと思うんです。そもそも「遠く」だから新しい発見やものに出会えるとも限らない。「遠くへ」という意味をちょっとズラしていくことだってできると思います。僕自身、かつては出張で月に3回も東京に行くこともありましたが、この2年で2回しか行ってません。でも、それで何か不便があったかと言えばそんなこともない。だから、これまでのように当たり前にビジネスマンがあちこち泊まりがけで出張するスタイルは、今後も一部は元に戻らないだろうと思います。実際、遠くの人とも今ならオンラインで繋がることはできる。そういう意味では距離との付き合い方が変容した2年だったのかもしれませんね。
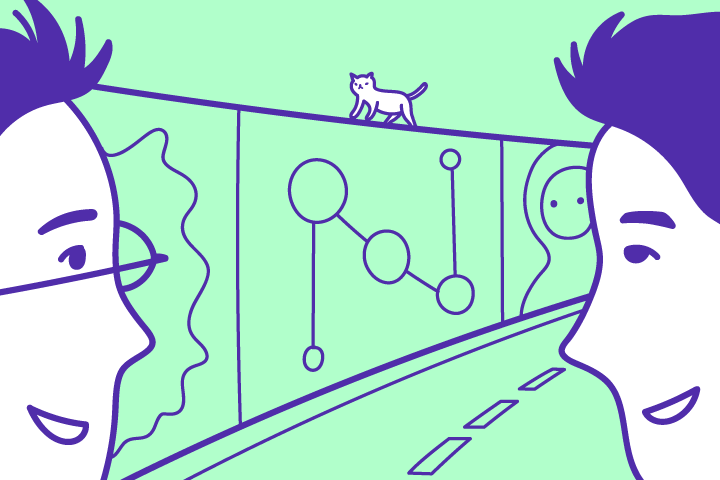
そもそも、アートは誰のもの?
――今の松村さんのお話は阿部さんの映画『街は誰のもの?』にも繋がっていくお話ですね。阿部さんが映画において取り上げていたグラフィティやスケートボードというカルチャーには、街で生活しながらその街をつくり直していく、あるいはその街を再発見していくような側面があると思います。それらもまた、水平的な移動ということとは別の意味で「遠くへ」と向かうことだといえるのかもしれません。たとえば東京のような街でも、街の解像度を上げることで今まで見えなかった街が見えてくることがある。水平方向の移動ではなく、アンダーグラウンドなカルチャーに触れてみたりすることで、垂直方向に潜っていくこともまた、「部屋から遠くへ」の一つの作法なのかもしれません。
阿部:そうですね。ブラジルにおいてはストリートカルチャーが全然アンダーグラウンドなものじゃなくて市民権を得たものとしてあるとはいえ、そうしたカルチャーを体験して日本に戻ってくると、やっぱり日本の街の見え方も変わってくるんです。日本の場合、規制が厳しいというのもあり、ストリートカルチャーは割と隠れた場所にあって、自分で潜っていかないと辿り着けなかったりする。ネットで検索しても出てきませんしね。ただ、そういうところもまた魅力的だったりするんですよ。グラフィティというのは、その下に存在するアンダーグラウンドなカルチャーの表面だけ可視化されたようなものだとも僕は思っていて、実はそうした印が街中にたくさん散らばっているんです。ここ2年でそうした街への解像度を持つことができた人も多いんじゃないかなと思いますね。

阿部航太さんが監督したドキュメンタリー『街は誰のもの?』では、ブラジルに滞在してグラフィティ、スケートボード、デモなどの路上における人々の営みに迫った。
―—松村さんはグラフィティを始めとするストリートカルチャーについてはどのような印象をお持ちですか?
松村:僕自身はその分野には決して明るくはないんですが、阿部さんの映画を観てなるほどと思ったことがありました。あの映画は大きく三つの部分から成り立ってて、それぞれグラフィティの人たち、スケートボードの人たち、あと路上でデモをしたり演説をしたり座り込んだりしている人たちが被写体となっています。それらが一つの映画の中で一緒に並べられたことで、グラフィティを描くことも、街でスケボーをすることも、メガホンで窮状を訴えたりデモをしたりすることも、実は同じ地平にあるんだ、同じように街をつくりなおす「建築的な介入」なんだということを気づかせてもらったんです。
そういう視点で考えてみると、街でお店を開くようなこともまた街への介入のひとつとして見えてくる。たとえば私が岡山で普段からお世話になっている「スロウな本屋」という小さな本屋さんがあるんですけど、そこは三軒長屋の一軒を使っていて、本が置かれているのはほんの二間。さらにお店に入るときに靴を脱いで上らなきゃいけないんです。コロナ前はイベントもたくさんやられていたんですが、いつの間にかゆるやかな常連さんたちのコミュニティのようなものも生まれていたんです。店主の小倉さんが体調を崩されたとき、さっとお客さんの女性たちがさりげなくサポートして、手を差し伸べていたり。これもまた街をつくりなおす行為なんですよね。そういう小さな場から、普段は出会えない人とのつながりも生まれて、街にいる感覚も変わっていくんです。

「ゆっくりを愉しむ」をコンセプトに、店主が選んだ絵本と暮らしの本を揃える本屋「スロウな本屋」。岡山駅の近くに店を構える。住所は岡山県岡山市北区南方2-9-7。
あるいは岡山市の奉還町商店街に「ラウンジ・カド」という飲食できるユニークなお店があります。建物全体がイベントスペースにもなってて、映画の上映会やトークショーなどが行われるんですけど、いろんなおもしろい企画があるんですよ。最近は岡山の伝説的なライブハウス「ペパーランド」を立ち上げた能勢伊勢雄さんが連続講演会をやられていて、戦後いかにして焼け野が原だった岡山が復興して、芸術文化運動が起きたのかという話をされていました。そうしたイベントを通じて志を持った人たちがつながって、それがまた別の動きを呼び込んでいく。これもまた街をつくっていく行為だと思います。

岡山県、奉還町4丁目の商店街に店を構える「ラウンジ・カド」で開催された能勢伊勢雄さんのトークイベントの様子。ライブ、スナック、トークなどさまざまな催しが開催される。住所は岡山県岡山市北区奉還町4-7-22。
アートを鑑賞するというと、どこか受動的な行為のように思ってしまいがちですが、実はそんなことはないんですよね。特に阿部さんの映画を観て以来、強くそう思います。大事なことは自分がどうやってこの街の中で生きるか。何を街に投げかけるか。それがストリートで絵を描く行為とつながっている。その観点からは、誰しもが表現者になりうるんです。阿部さんのお話しで印象的だったのは、ブラジルのストリートでは絵が上手い人の作品の隣に恥ずかしげもなく下手な人も描いていること。アートが誰もが参加しうるものとして開かれてるんだな、と。鑑賞者もまた制作者になりうるんだと気づかせてもらいました。

ブラジル、べロ・オリゾンチのファベーラ(貧困街)のイベントでグラフィティが描かれる。(映画『街は誰のもの?』より)
阿部:ブラジルの初等教育には義務教育としての美術や図工がないんですよね。お金持ちの子供達が通う私立にはあるんだけど、基本的には美術教育は行われてない。それにも関わらずみんなアートがめちゃくちゃ好きなんですよ。アートの敷居がものすごく低い。それって日本だとないことですよね。日本で「アート好きです」というためにはアーティストの名前やアートの文脈的な背景とか色々なことを知っていなきゃいけないみたいな感じがある。敷居が高いんです。一方、彼らはそんなの全然知らないけど、みんな口を揃えて「アートって素晴らしいじゃん」と語る。その衒い(てらい)のなさが衝撃的だったんです。
おそらくブラジルがそういう雰囲気なのは街中にあるグラフィティによるところも大きいように思います。実際、彼らに好きなアートの画像を見せてもらったりするとそれはグラフィティだったりする。日本は特に、現代美術、近代美術、ストリートアートみたいなカテゴリーを強調したがるところがありますけど、向こうではそこがかなりフラットになっていて、少なくとも市民レベルではアートという言葉の中に全てが包含されているという印象があるんです。その背景にはいま松村さんがおっしゃっていたような部分、「誰もがアートの鑑賞者であり同時に制作者である」という意識があるように思いますね。
『偶然の装丁家(就職しないで生きるには)』著/矢萩多聞
ノンフィクション、学術書、絵本などこれまでに600冊以上の本を手掛けた矢萩さんの自叙伝。晶文社/2,393円

松村:この前、矢萩多聞さんという画家でブックデザイナーの方の著書『偶然の装丁家 』の書評を書いたんです。矢萩さんは、小さいころから絵を描くのが好きだったそうですが、小学生の頃はずっと図工や美術の成績が1だったらしいんですね。なぜかというと締め切りがあるから。矢萩さんは自分なりに時間をかけて描きたいので学期中に作品を仕上げることができない。絵を提出できないと描かなかったことにされてしまうわけです。しかも中学生になったら美術の先生がああしたらいい、こうしたらいい、と言ってくる。結局、矢萩多聞さんは不登校になってしまったんです。
皮肉な話ですよね。美術教育があるばかりに本当に好きな絵がともすれば苦痛になってしまうんですから。子供は大抵が絵を描くことが好きなはずなんだけど、いつからかそれが誰かに査定され、評価され、貶められる何かに変わってしまう。そういう仕組みが教育システムの中にあることでアートの敷居も高くなってしまう。本来みんながアートの作者になりうるのに、教育があることで描ける人、描けない人、上手い人、下手な人の間に線が引かれてしまう。もちろん絵の技術や能力もあるんだろうけど、決してひとつの基準が全てではないですよね。
阿部:そうですよね。ブラジルでは美術の初等教育はないけど、子供向けのグラフィティのワークショップがけっこう行われていて、すごく盛り上がっているんです。日本にも子供たちがトンネルなどの公共物に描く壁画のようなものがありますが、ああいうのを見るとすごく暗い気持ちになります。なんか大人の都合で子供たちが駆り出されて、やらされている感じがして。一方、ブラジルでは街中にグラフィティがあるから、ワークショップにおいても子供たち自身が自分が何をしようとしているかをすごく分かってるんです。みんな奪い合うようにスプレーに群がっていて、絵を描くことを楽しんでる。日本の査定する教育とは全然違う教育だなと思いましたね。
後編では、ストリートアートの持つ政治性の話に始まり、そもそも人はなぜアートを鑑賞するか?という根本的な問いを二人は考えます。
information

松村圭一郎 著作『くらしのアナキズム』
“国家は何のためにあるのか? ほんとうに必要なのか?”━━文化人類学の視点で国家がない状態での人々の暮らしを思考し、分析した一冊。国家に頼らない様々な民族の暮らし、過去の文献を通して、私たちが自分たちの手で公共を作り出すことができること論じる。ミシマ社/1,980円

阿部航太 監督作品『街は誰のもの?』
「存在したかったんだ。その街に存在したかったんだ。」グラフィテイロ(グラフィティアーティストの現地での呼称)がつぶやく背景に広がるのは、南米一の大都市サン・パウロ。そこには多様なルーツ、カルチャーが混沌とするブラジル特有の都市の姿があった──阿部航太がブラジルの4都市を巡りストリートの表層と深層を撮影したドキュメンタリー作品。
シアター・イメージフォーラム(東京)、名古屋シネマテーク(愛知)に続き、2022年2月11日 京都みなみ会館(京都)、2月12日 シアターセブン(大阪)にて公開
machidare.com
DOORS
-min.jpg)
松村圭一郎
文化人類学者
岡山大学文学部准教授。専門は文化人類学。エチオピアの農村や中東の都市でフィールドワークを続け、富の所有と分配、貧困や開発援助、海外出稼ぎなどについて研究。著書に『うしろめたさの人類学』(ミシマ社)、『これからの大学』(春秋社)、『はみだしの人類学』(NHK出版)、『くらしのアナキズム』(ミシマ社)などがある。
DOORS

阿部航太
デザイナー/文化人類学専攻
2018年よりデザイン・文化人類学を指針にフリーランスでの活動を開始。2018年から2019年にかけてブラジル・サンパウロに滞在し、現地のストリートカルチャーに関するプロジェクトを実施。2021年に映画『街は誰のもの?』を発表。近年はグラフィックデザインを軸に、リサーチ、アートプロジェクトなどを行う。2022年3月に高知県土佐市へ移住し、海外からの技能実習生と地域住民との交流づくりを目指す「わくせいPROJECT」を展開している。
volume 01
部屋から、遠くへ
コロナ禍で引きこもらざるを得なかったこの2年間。半径5mの暮らしを慈しむ大切さも知ることができたけど、ようやく少しずつモードが変わってきた今だからこそ、顔を上げてまた広い外の世界に目を向けてみることも思い出してみよう。
ARToVILLA創刊号となる最初のテーマは「部屋から、遠くへ」。ここではないどこかへと、時空を超えて思考を連れて行ってくれる――アートにはそういう力もあると信じています。
2022年、ARToVILLAに触れてくださる皆さんが遠くへ飛躍する一年になることを願って。
新着記事 New articles
-
SERIES

2026.02.11
光と物質の「現象」が立ち上がる場所から、絵画のセカイへ / 連載「部屋は語る〜作家のアトリエビジット〜」Vol.3
-
SERIES

2026.02.11
「自分の手で、つぎはぎした空間は心地いい」オルネ ド フォイユ店主・谷卓の、未完成なものたちへの眼差し / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.44
-
NEWS

2026.02.06
松坂屋名古屋店でアートシーンを牽引する国内14ギャラリーが集結する「ART 365」が開催
-
INTERVIEW

2026.02.05
アーティスト・小林繭乃と三平硝子によって生み出されるモンスターたち / 二人展「Monster:モンスター」出展インタビュー
-
SERIES

2026.02.04
90年代英国美術の革新を辿るテート美術館展から、映像の現在地を問う恵比寿映像祭まで。 / 編集部が今月、これに行きたい アート備忘録 2026年2月編
-
REPORT

2026.02.04
TOKYO ART BOOK FAIR 2025で1万円あったら何を買う? #2 服部恭平、田部井美奈、井上岳(GROUP)に聞いた

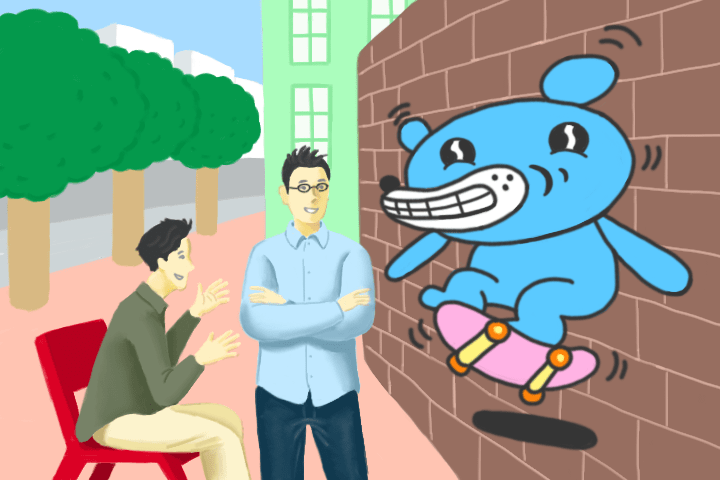
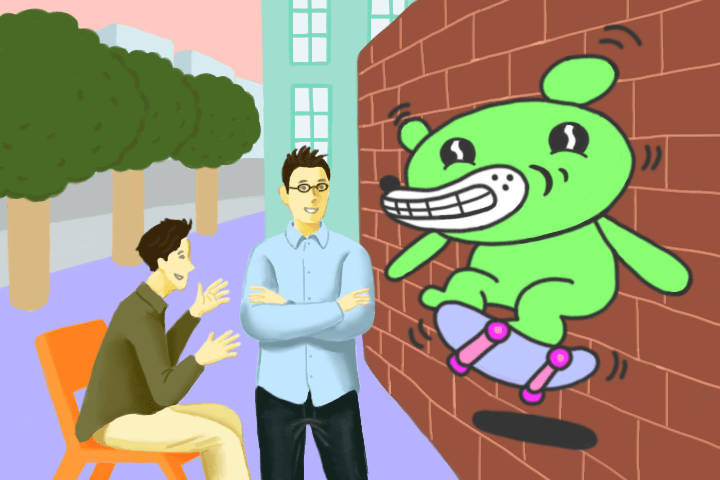



-min.jpg)