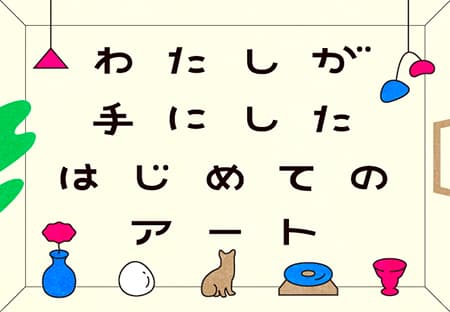- ARTICLES
- リスペクトから生まれる「奥行きのある」クリエイティブ。アートディレクター・千原徹也に影響を与えた作品 / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.33
SERIES
2025.03.12
リスペクトから生まれる「奥行きのある」クリエイティブ。アートディレクター・千原徹也に影響を与えた作品 / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.33
Photo / Daisuke Murakami
Edit / Miki Osanai & Quishin
自分らしい生き方を見いだし日々を楽しむ人は、どのようにアートと出会い、暮らしに取り入れているのでしょうか? 連載シリーズ「わたしが手にしたはじめてのアート」では、自分らしいライフスタイルを持つ方に、はじめて手に入れたアート作品やお気に入りのアートをご紹介いただきます。
お話を聞いたのは、アートディレクターの千原徹也さん。CDジャケットや企業広告、雑誌の表紙づくりなど、手がけるアートワークは多岐に渡り、2023年には映画『アイスクリームフィーバー』を公開するなど、映画監督としても活躍しています。
「はじめて手にしたアート」は、有名絵画からインスピレーションを受けてつくられたDELVAUX(デルヴォー)のレザーバッグ。千原さんもそこからインスピレーションを受け、自著『これはデザインではない 「勝てない」僕の人生〈徹〉学』の刊行に至ったそうです。「過去の作品に対するリスペクトを、どのように継承していくかを大切にしてきた」というお話からは、アウトプットに活きるインプットの心得を学ぶことができます。
太田メグ / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.32はこちら!
# はじめて手にしたアート
「『これはデルヴォーではない』という言葉の裏にある、考え方に惹かれました」

厳密には「はじめて手にしたアート」ではないですが、アートの文脈で紹介するとおもしろいと思うのが、会社を立ち上げたときに購入した「DELVAUX(デルヴォー)」のバッグ。正面にはフランス語で「これはデルヴォーではない」とメッセージが刻まれています。
この言葉は20世紀初頭に活躍した画家であるルネ・マグリットの作品『イメージの裏切り』からインスピレーションを得たもので、このマグリットの油彩画にはパイプが描かれていて、下に「これはパイプではない」とメッセージが記されるんです。
デルヴォーとしては、「(つくる人や観る人が)パイプだと思ってしまったら、それはパイプでしかなくなる」と思った。そして、ブランドの職人たちにも「デルヴォーのバッグをつくっていると思っていたら常識を超えられないから、デルヴォーではなく新しいアートを生み出すような感覚でつくってほしい」とバッグを手がけさせた経緯があります。

DELVAUX(デルヴォー)のルーモア
こういった考え方は僕自身とても大切にしてきたことなので、心から共感しました。たとえば、アイドルのCDジャケットをデザインする依頼がきたときに、アイドルのCDジャケットをつくろうとしてしまうと、世の中にあるそれらを超えられない。だから「これはアイドルのCDジャケットではない」という否定から入るなど、枠から外れて物事を考えていく必要がある。そういう意識でデザインの仕事をしています。
100万円ほどのバッグなのですが、自分のアイデンティティの象徴として、会社(株式会社れもんらいふ)を立ち上げた2011年のタイミングで、迎え入れました。
# アートに興味をもったきっかけ
「10代の頃から触れてきたレコードや漫画、映画など、ポップカルチャーの延長線上に、アートがありました」

シンガーソングライター・大瀧詠一さんの初となるライブアルバム『NIAGARA CONCERT ’83』。レコードのジャケットはイラストレーターの永井博さんが手がけている
幼少期から漫画や映画が好きで、カルチャーを通じて無意識のうちに、アートに触れてきたように思います。
自分の中でしっかりと「アートに触れている」と意識したのは、たぶん、ポップカルチャーの象徴であるアンディ・ウォーホルが描いたヴェルベット・アンダーグラウンドのバナナのジャケットから。10代後半からレコードを買うようになり、アートワークに込められたストーリーにも興味を持ちはじめました。
10代の頃は、地元・京都のクラブにも通っていて、そこでDJのテイ・トウワさんや、アートディレクターとしてCDジャケットを手がけているヒロ杉山さんと出会ったことも、アートへの関心が膨らんだきっかけだったと思います。アートをアートとして意識しながら触れていたわけではなく、「ポップカルチャーの一部」として自然に接してきましたね。
# 思い入れの強いアート
「自分が生きてきた文脈と重なるものを買いたい。いつかウォーホルの作品も、買ってみたいですね」

憧れのデザイナーであるヒロ杉山さんに描いてもらった、シルエットアート。トレードマークのハットとメガネ部分は立体になっている
僕はパッと感覚的にモノを買うことは少なくて、自分の生きてきた文脈と重なる作品しか買いたくない。永井博さんの絵がまさにそれです。
10代の頃は、1980年代のシティ・ポップで一世を風靡した、大瀧詠一さんのアルバム『A LONG VACATION』のジャケットに魅了されていました。それを手がけたのが、永井さんです。

大瀧詠一さんの自宅のプールを上から見た様子を描いた、永井さんの作品。「自分の子どもたちが大きくなっても、家の真ん中にプールがあったなと思い出してほしい」と自宅のリビングの中心に飾っている
永井さんとは、幸運にも2016年に、メガネブランド・Zoffのサングラスキャンペーンのビジュアルデザインで仕事をご一緒しました。僕からご依頼したのですが、「80年代の自分を知っているなんてうれしい」と話してくれ、僕も本当に満たされたことを覚えています。永井さんに憧れて過ごしてきた時代と現在が、リンクしたかのような気持ちになりましたね。
それから、40歳の誕生日に妻がプレゼントしてくれたレオナール・フジタ(藤田嗣治)の『四十雀』も、思い入れ深い作品です。

レオナール・フジタの『四十雀』。中にはフランスの小説家であるジャン・コクトーの詩が書かれている
家族で藤子・F・不二雄ミュージアムを訪れた際、藤子先生が「漫画家として成功してはじめて買ったアート」としてフジタの絵を展示していました。僕は小学生の頃から藤子先生に影響を受け、漫画家を夢見ていた時代もあったので、「いい話だなあ」と妻に話していたんです。その何気ないひと言を覚えてくれていた妻が、サプライズで贈ってくれたのがこの絵でした。
それまでは「アートを買う」ということにあまり興味がありませんでしたが、ひとつ買うと、ほかの壁にも飾りたい欲が湧き出てくるように。それこそ、アンディ・ウォーホルの絵とか、いつか買ってみたいですね。
# 奥行きのあるクリエイティブ表現
「過去の作品へのリスペクトをどのように継承するかを考えながらつくることが、奥行きのある作品につながる」

ダイニングにはお子さんの絵も飾られている
アートディレクターになって14年、「0から1を生み出している人」とよく見られるのですが、実際には、「何をリファレンス(reference)として取り入れてつくるのか」を常に考えてきました。
リファレンスというのは、自分が何かをつくる上で参考にする“資料”のこと。デザインをするにしても、映画をつくるにしても、過去の作品へのリスペクトをどのように継承していくかを考えながらつくることが、「奥行き」のある作品につながると思っています。
たとえば、僕の著書である『これはデザインではない 「勝てない」僕の人生〈徹〉学』(2022年)も、デルヴォー、マグリットへのリスペクトと、「これはデザインではない」という考え方を継承していきたいという思いを込めて、このタイトルをつけています。
デザインひとつとっても、今の時代、画像検索サイトで集めた素材を直感を頼りに組み合わせて“それっぽいもの”をつくることはできます。だけどそうやってつくったものにはストーリーがなく、アウトプットに対して自分で意図を説明することができない。何もないところから作品をつくっても、平坦で表面的な表現になってしまうんです。

リファレンスを取り入れることの大切さを実感したきっかけのひとつが、カンヌ映画祭に行くようになったことでした。数年前から足を運ぶようになったのですが、僕たち日本人よりも現地の審査員や会場にいる人たちのほうが、日本映画や日本のアートの文脈を理解していたりすると知ったんです。
コム・デ・ギャルソンの良さや、日本映画はどの時代がどうおもしろいかを、海外の人たちが語れて、自分たち日本人が語れないのはカッコ悪い。それに、自分がつくりたいジャンルの歴史・文化的背景や、過去作品へのリスペクトなどを何も取り入れず、ただその時々の流行だけを追いかけるような作品になってしまうと、なんの文化もアイデンティティも継承していくことができない。そういったことを肌身で感じました。
# アートのもたらす価値
「映画でもアートも『問い』を持って見つめることが、アウトプットに活きる知識になる」

伊藤桂司さんのグラフィックアート「KIRINJIのジャケットや愛知万博のポスターなどを手がけてきた伊藤さんのグラフィックの雰囲気を子どもたちにも感じてもらいたいと、あえて子ども部屋の前に飾っています」
奥行きのあるクリエイティブを生み出すために、前提としていろんな作品に触れておくことが求められるのですが、アウトプットに生かせるインプットにするためには「自分が誰かに説明できる」くらいまで、自分のものにすることが大切です。
たとえば映画を観るとき、一度目はエンタメとして消費するだけで精一杯かもしれません。でも、2回、3回、10回と繰り返し観ることで「このカットってこういう意味があったんだ」とわかったり、「どういう狙いで撮ったんだろう」と監督の意図を考えたりするようになる。そうやって得ていったものを「知識」と呼ぶのだと思いますし、その体験を心に溜めながら生きていくことが、奥行きのある作品づくりにつながっていくと思います。

アートを観るときも、「かっこいい」「きれい」で終わってはもったいない。世の中に長く残る作品には、時代背景、描かれた街、アーティストの人間関係や環境など、考えたり調べたりしなければ見えてこない作者の想いが込められているもので、「なぜこの絵はこんなに暗いのだろう?」「どうしてこんなにカラフルなのだろう?」という疑問への答えもそこにある。
なんとなく「このアートいいな」という感覚的に楽しむことも貴重な経験ですが、何かを生み出したいという欲求がある人は、そこからもう一歩踏み込んで、問いを持って作品を見つめてみてほしいですね。
DOORS

千原徹也
アートディレクター、映画監督
1975年京都府生まれ。広告(H&Mや、日清カップヌードル×ラフォーレ原宿他)企業ブランディング(ウンナナクール他)、CDジャケット(桑田佳祐 「がらくた」や、吉澤嘉代子他)、ドラマ制作、CM制作など、さまざまなジャンルのデザインを手掛ける。またプロデューサーとして「勝手にサザンDAY」主催、東京応援ロゴ「KISS,TOKYO」発起人、富士吉田市の活性化コミュニティ「喫茶檸檬」運営など、活動は多岐に渡る。長年の夢だった映画監督としての作品「アイスクリームフィーバー」が2023年7月に公開。2024年春開業、原宿の商業施設 東急プラザ原宿「ハラカド」にれもんらいふを移転させ、新たなプロジェクトに取り組む。
新着記事 New articles
-
SERIES

2026.02.11
光と物質の「現象」が立ち上がる場所から、絵画のセカイへ / 連載「部屋は語る〜作家のアトリエビジット〜」Vol.3
-
SERIES

2026.02.11
「自分の手で、つぎはぎした空間は心地いい」オルネ ド フォイユ店主・谷卓の、未完成なものたちへの眼差し / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.44
-
NEWS
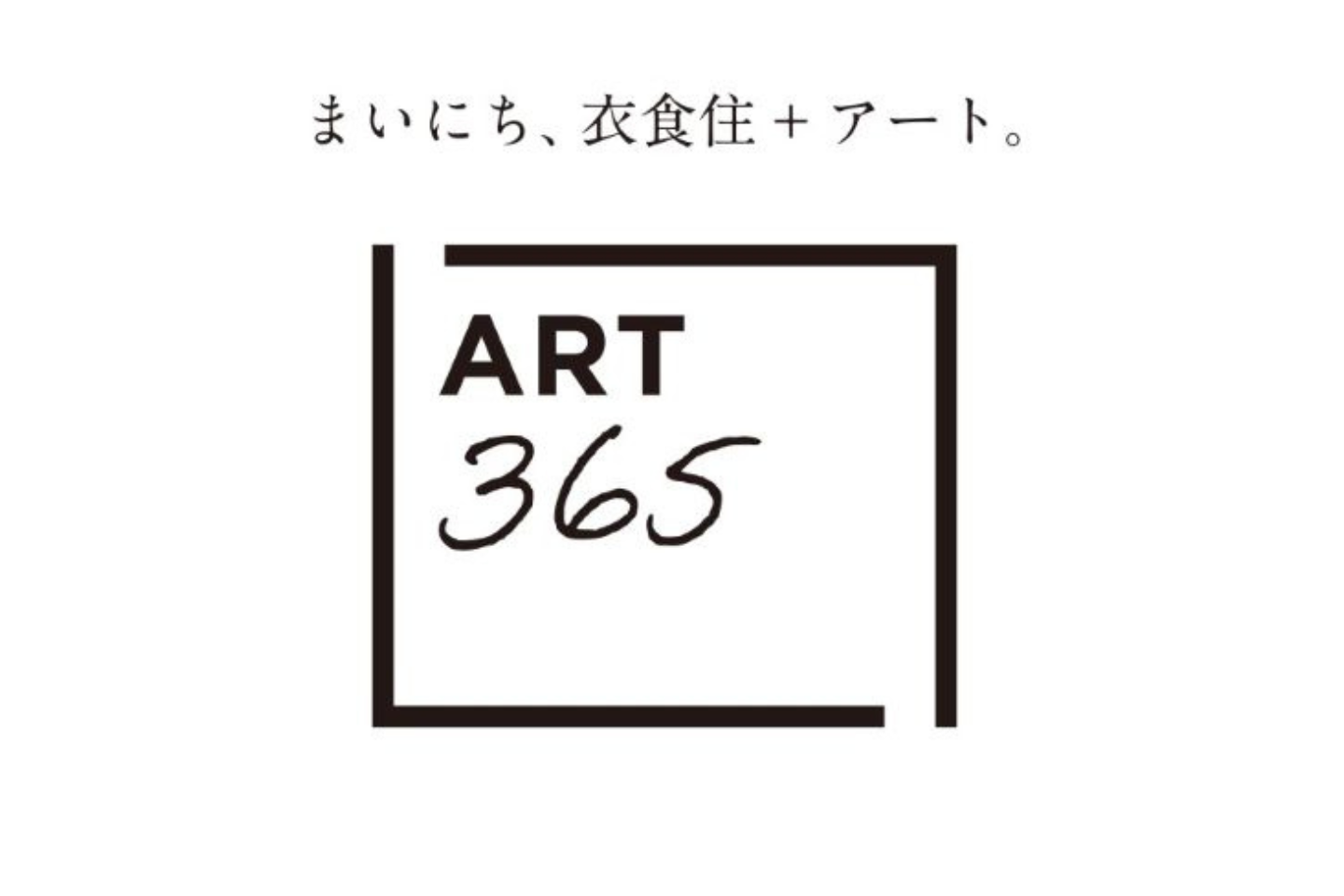
2026.02.06
松坂屋名古屋店でアートシーンを牽引する国内14ギャラリーが集結する「ART 365」が開催
-
INTERVIEW

2026.02.05
アーティスト・小林繭乃と三平硝子によって生み出されるモンスターたち / 二人展「Monster:モンスター」出展インタビュー
-
SERIES

2026.02.04
90年代英国美術の革新を辿るテート美術館展から、映像の現在地を問う恵比寿映像祭まで。 / 編集部が今月、これに行きたい アート備忘録 2026年2月編
-
REPORT

2026.02.04
TOKYO ART BOOK FAIR 2025で1万円あったら何を買う? #2 服部恭平、田部井美奈、井上岳(GROUP)に聞いた