- ARTICLES
- 【後編】テクノとドローイング作品の関係性とは? / 連載「作家のB面」Vol.2 村山悟郎
SERIES
2022.06.10
【後編】テクノとドローイング作品の関係性とは? / 連載「作家のB面」Vol.2 村山悟郎
Edit / Eisuke Onda
Photo / RAKUTARO
Illustration / sigo_kun
アーティストたちが作品制作において、影響を受けてきたものは? 作家たちのB面を掘り下げることで、さらに深く作品を理解し、愛することができるかもしれない。 連載「作家のB面」ではアーティストたちが指定したお気に入りの場所で、彼らが愛する人物や学問、エンターテイメントなどから、一つのテーマについて話してもらいます。
第二回目に登場するのは村山悟郎さん。渋谷パルコにあるライブストリーミングスタジオDOMMUNEで大好きな「テクノ」の話をはじめたら、熱い思いは止まらず取材は想定外のロングセットに……。テクノから学んだと語る「持続と変化」することの大切さ、そのイズムをどのように作品へと昇華してきたのか? 村山さんがつくる緻密なドローイング作品の深層に潜ります。
前半ではテクノの話からなぜ村山さんがアーティストの道を進むことになったのかを掘り下げました。
「持続と変化」を絵画で表現するには?

――前半で話していた「持続と変化を両立できなければ良いDJにはなれない」という話がとても面白かったのですが、この「持続と変化」は村山さんの作家活動において、どのような影響を受けているのですか?
まず、この持続しているという感覚が何によって生み出されているのか、という点に関心があるんです。持続というのは、一つの情動性だと僕は考えています。たとえば「落ち着く」みたいな気分もそう。「誰もこの空間で怒ってる人がいない」みたいな周囲を包むまったりした情態もひとつの持続感。でも誰かがいきなり激昂して部屋を出ていっちゃった場合、その気まずい感じや緊張から、なんとか引き戻さなきゃいけないみたいな働き、つまり変化が生じるわけですよね。そうした様々な感情に伴って生じる変化や時間感覚の在り方がある。怒りの感情とかはかなりドラマチックな変化で、持続を打ちこわすジェットコースターみたいなもので、時間感覚も乱れますし、その怒りもそのうち収まるということを我々は経験的に知っている。つまり、感情には立ち上がってから減衰してゆくまでの時間性があるわけです。じゃあ逆にフラットな持続性の感情をメロディで表現するとしたらどんなだろう、とかね。
ちょっと比喩的に言うと、誰も怒っていない状態を持続しながら、かつ変化もし続けてていくような作品をいかに作り出すことができるか、そういう持続と変化の両義的な状態により強い興味があるんです。
――つまり、持続感というのは事実の水準ではなく印象の水準に依拠しているということですね。実際に何かが起こっているかどうかを問わず、ある一つの状態が持続しているように感じられるということ自体に関心がある、と。
脳の働きや主観性あるいはその社会的な現れの問題なんです。たとえばシンセサイザーがビーって一音だけ鳴り続けているというようなことではない。それこそ最近のAphex Twinはそうした「持続と変化」の新しい形みたいな表現を試みているように僕は感じてます。ここのところ、組曲みたいな長い曲を出してるんですよね。例えば「SYRO」というアルバムの「XMAS EVET10 (Thanaton3 Mix)」という曲。1曲が4セクションくらいに分かれてて、途中で完全に曲調が変わったりする。交響曲みたいな楽章とも違っていて、使う音源も変わっていくんだけど、同じ一つの曲であるというような持続性は保たれてる。そういうことがなぜ可能なのか、あるいはどうしてそれが一個の曲として持続しているという風に感じられるのか。そういうところを分析しながら聴いています。
村山さんがよく聴くイギリスのアーティストのAphex Twin。テクノ、アンビエント、エレクトロニカ、ドラムンベース、アシッド・ハウスと多彩なジャンルに影響を受けたダンスミュージックを作っていた。
たとえば貝殻の場合、その模様が生成する規則はその貝においては基本的に一定なんです。環境の影響は受けますけど途中で規則自体が変わって別の模様パターンが出るというようなことはない。でも人間の精神の場合は自己を維持したままもう少し大胆なモードチェンジみたいなものがありますよね。あるいは生き物でも、おたまじゃくしがカエルに変態するように、同じ個体であることは持続しているけど明らかに別の状態になるってことはありえる。そういう「持続と変化」のあり方が自然界にもあるし、Aphex Twinの最近の試みはそういう表現として僕は受け止めてます。それを自分の制作にも活かせるんじゃないかということは考えていますね。

村山さんの最近の展示会場には制作で影響を受けた貝殻を展示することも。「この貝殻のパターンが絵のキャプションのような効果をもたらしてくれる」と村山さん
『バリ島人の性格ー写真による分析』
著 / グレゴリー ベイトソン、著 / マーガレット ミード、 翻訳 / 外山 昇
文化人類学者のグレゴリー・ベイトソンは『バリ島人の性格―写真による分析』で、1930年のバリ島の風俗、思考、社会性をリサーチしてまとめた。国文社 / 5,000円
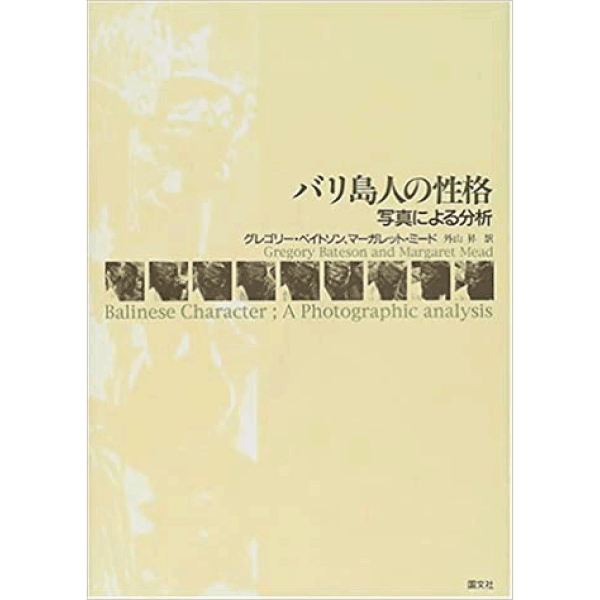
――なるほど。村山さんの美術や音楽に対する嗜好性からは、今日の社会構造に対するある種の批判精神のようなものも感じるのですがいかがでしょう? たとえばAメロ、Bメロ、サビみたいな楽曲構成には、平日を我慢しながら働いて週末は思いっきり弾けるというようなライフスタイルを連想するんです。一方で反復系の音楽にはそうしたメリハリがあまりなくて、平日でも休日でもない、よく分からない状態がヌメヌメと微小に変化しながら続いていくような感じがある。そこにオルタナティブな社会の可能性が潜在しているようにも思います。それこそ、会社通いのないトライバルな社会の伝統音楽は構成がミニマルなものが多いですよね。
面白いですね。グレゴリー・ベイトソンがバリ島の伝統音楽と部族社会のあり方を結びつけて考え、さらにそれを西洋近代社会と対比して論じていたことがありました。現代社会というのは基本的に、ベイトソンに言わせれば相互応酬型の形式で動いている。たとえば核軍拡競争。あれも国家間の応酬によって軍拡が盛り上がりすぎてしまったひとつのケースですよね。一方でバリの社会はそうした相互応酬型にはなっておらず、応酬的なコミュニケーションを緩和するよう設定されていて、それがバリ島の伝統音楽にも表れているとベイトソンは言うんです。そういう意味では盛り上がりすぎる音楽は危ないとも言える。僕自身、そういう相互応酬型のハイテンションなコミュニケーションは苦手な方で、「もっとノッてこいよ」みたいに煽られてもノレないところがありますから。

グレゴリー・ベイトソンの考えに触発されて村山が制作したのが『Wall drawing / coupling』。 2010 / photo by Ken Kato / supported by Shiseido Gallery
――ベッドルームテクノの人としては(笑)。
そうそう(笑)。ガーッと盛り上がって消耗するよりも、もっと持続していく感じでいこうよという気持ちがある。それは個人的な音楽の嗜好としてもそうですね。トランスやEDMのように、分かりやすい形で感情を誘導しようとしてくるような音楽に対しては、ちょっと斜に構えてしまうところがあります。そう簡単にはノセられてなるものか、と。とはいえ、僕も一時期、EDMにはハマっていたんですが(笑)。演歌のようなコブシを効かせた電子音楽として。
合奏ではない、協働のあり方の可能性

――では最後に話を戻すと、ベッドルームテクノリスナーだった少年時代を過ごしていた村山さんも、やがては実際にクラブに足を運ぶようになったわけですよね。音楽との関わり方に変化はありましたか?
いろんなジャンルの音楽を聴けるようになりましたね。でもやっぱりクラブでも僕は一人で来て、誰とも絡まずに帰っていくタイプでしたね。ただ、クラブには僕みたいな人たちもチラホラいて、僕にはそういう人たちが光って見えてました。「お前もか、俺もだぞ」みたいな感じで(笑)。だからクラブで出会った友達とかいないんですよ。
――(笑)。ただ、そうとはいえ、ある場、ある状況をフィジカルに他人と共有しているわけですよね。ある種の自閉的な状態が維持されたまま行われるコミュニケーションのようなものも、そこにはあったんじゃないですか?
それはありますね。ある存在が独立して運動しているだけで、別に積極的に絡もうとしていなくても、カップリングのようなことが起こっていたりはしますから。生物界でいうと花とミツバチの共進化のようなものです。要は自己が意図して何かに介在しようとするのではなく、常に既に連動しているという状況があり、クラブにおいてもそんな感じがありました。実は作品制作の上でもこのようなカップリングについては考えています。たとえば瀬戸内国際芸術祭2022(*1)に出展している作品の中に、日本家屋の床の間に使用されていた古材を再利用して絵を描いた作品があるんですが、その木材の木目は広葉樹特有の複雑なパターンになっていて、僕はその木目に沿って貝殻模様のパターンを描いているんですよね。その二つのパターンはそれぞれが自律して生成しているんだけど、そこにはある種の媒介するコミュニケーションがあって第三のパターンをつくりだしている。
*1……瀬戸内国際芸術祭2022に<生成するドローイング -日本家屋のために2.0>を出展。村山さんいわく、「貝殻模様から生成させたパターンが壁全面に展開している作品になります。一時的に決められた規則を適応し続けてパターンを生成していったんですけど、そのパターンは必ずしも周期的ではないんです。ただ、カオス状態でもない。そういう中間状態のパターンを生成する規則というのがあり、それが貝殻とか自然界にも見出されているんです。その規則自体はコンピューターでジェネレートできるような単純な規則でもあるんですけど、それを複数の人間が人力によって描いていくことで、人間のエラーとかもそこに入ってきています。瀬戸内海の男木島に滞在しながら描いたんですが、滞在中はどういう風に時間が作られるかということを考えていました。だから、この作品ではそうした時間性をテーマに作品を見せたいと思ってます」

男木島の民家の壁一面にドローイングを描いた作品『生成するドローイング- 日本家屋のために2.0』。瀬戸内国際芸術祭2022 男木島 / Photo:KIOKU Keizo / 瀬戸内国際芸術祭2022 / ©Goro Murayama
そもそもオートポイエーシスの理論自体がそういうものになっていて、構造的カップリングというんですが、自律的に自己は出現していくんだけど、その時すでに環境との連動が起きているんですよね。独我論ではないんです。誰かとコラボレーションする上での感覚も同じで、バンドのようにタイミングを合わせて合奏するのとは違う協働のあり方があると思うし、僕としてはそういう可能性を探っていきたいんですよね。制作中に音楽を聴いているのも、その音楽のイメージで描きましたというような直示的な関係ではなくて、その音楽によって制作行為に生成変化がもたらされる、そんな感じです。

建物の木の壁には木目に沿って貝殻パターンのドローイングを施している。約15名で制作しドローイングには微妙に書き手のズレが生じる。『生成するドローイング- 日本家屋のために2.0』より。瀬戸内国際芸術祭2022 男木島 / Photo:Goro Murayama / 瀬戸内国際芸術祭2022 / ©Goro Murayama
――村山さんはものすごくロマンチストなのかもしれませんね(笑)。言葉を介して理解し合うであったり、クラブで仲間たちとアゲアゲになって情動を交感させるであったり、そういう分かりやすい、ある意味では表層的なコミュニケーションとはまた別のしかたで、何かと何かが通じ合うことができる一筋の可能性のようなものをずっと探り続けているように見えます。
あははは、まあ、そういうところはありますよね。やっぱり言葉でコミュニケートするというのは限界があるじゃないですか。「そういう意味で言ったんじゃないのに」みたいなことが絶対に起こる。逆に何も言わなければ「なんで何も言わないんだ」みたいになる。どんなに丁寧に言葉を重ねてもミスコミュニケーションみたいなものが必ず生まれる。人間ってつらいな〜って思いますよね(笑)。でも、言語でも大事なのは対話の持続性、それは意味の確認ではなく、知性の連動としての会話だと思ってます。
実際のところ、僕たちは言葉だけでコミュニケートしてるわけじゃないんですよね。それこそ同じ空間にいる人間がどういう匂いを発散しているかということによってもコミュニケートはなされている。当人同士が意識しないところで作動しているパターンのようなものの方が、実はコミュニケーションの要素としては大きいんじゃないかとも思うんです。アートを制作する上ではそういう謎めいた感性を捨てちゃいけないとも思いますしね。
そういう意味ではできるだけ明晰にロマンチックなことを考えたいというのはあるのかもしれません。まあ…、そういうことを言うのもちょっと恥ずかしいところではあるんですが(笑)。

information

Painting folding -『これと合致する身体を構想せよ』2019
photo by Shu Nakagawa
ICC アニュアル 2022 生命的なものたち
新しいメディア・テクノロジーの動向に伴って、現代の社会におけるテクノロジーのあり方を、メディア・アート作品をはじめ、現代のメディア環境における多様な表現によって別の見方でとらえていく展示「生命的なものたち」。こちらの展示では村山さんの新作『Painting Folding 2.0』を発表。この作品はタンパク質の生成をテーマにしていると村山は語る。
「オートポイエーシス理論は自己組織化していくシステムを理論化したものだけど、そこには遺伝子のような仕組みは組み込まれてないんです。その点、たんぱく質の生成というのは基本的に鎖状になったアミノ酸配列が遺伝情報によって決定されている。遺伝情報によって指定されたアミノ酸の鎖が、生体環境に入ると折れ曲がって一つの立体構造、つまりタンパク質を作り出すんです。ここでは遺伝子によって系列化される情報系と、物質がある状況に置かれたら必ず同じ反応を起こすという物質系との二つの系が連動してある一つの立体構造が作り出されるということが実現してる。その情報と物質の両義的な状態から一つの立体が作られるということにこそ驚くべき自然の造形を認めることができるわけですが、今回はそうしたタンパク質生成のあり方をモチーフに新作を発表します」
会期:2022年6月25日(土)─2023年1月15日(日)
会場:NTTインターコミュニケーション・センター [ICC] ギャラリーB , ハイパーICC
展示の詳細は公式HP:https://hyper.ntticc.or.jp/
ARTIST

村山悟郎
アーティスト
1983年、東京生まれ、在住。博士(美術)。東京大学特任研究員。絵画を学び、生命システムや科学哲学を理論的背景として、人間の制作行為(ポイエーシス)の時間性や創発性を探求している。代表作「織物絵画」に見られるように、自己組織的なプロセスやパターンを、絵画やドローイングをとおして表現している。また近年は科学者とのコラボレーションによって、AIのパターン認識/生成や、人間の AIにたいする感性的理解を探るなど、表現領域を拡張しつづけている。2010年、shiseido art egg賞を受賞。2010-11年、ロンドン芸術大学チェルシーカレッジ MAファインアートコース(交換留学)、2015年、東京芸術大学美術研究科博士後期課程美術専攻油画(壁画)研究領域修了。2015-17年、文化庁新進芸術家海外研修員としてウィーンにて滞在制作(ウィーン大学間文化哲学研究室客員研究員)。2024年に東京大学比較文学比較文化で客員准教授を務め、現在は武蔵野美術大学映像学科および東北芸術工科大学大学院で非常勤講師を務めている。
DOORS

辻陽介
編集者・ライター
アートやタトゥー、ストリートカルチャー、文化人類学など様々な文化を耕すメディア『DOZiNE』の編集人。共編著『コロナ禍をどう読むか』(亜紀書房)。現在『BABU伝—北九州の聖なるゴミ』をDOZiNEで連載中。
新着記事 New articles
-
SERIES

2026.02.11
光と物質の「現象」が立ち上がる場所から、絵画のセカイへ / 連載「部屋は語る〜作家のアトリエビジット〜」Vol.3
-
SERIES

2026.02.11
「自分の手で、つぎはぎした空間は心地いい」オルネ ド フォイユ店主・谷卓の、未完成なものたちへの眼差し / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.44
-
NEWS

2026.02.06
松坂屋名古屋店でアートシーンを牽引する国内14ギャラリーが集結する「ART 365」が開催
-
INTERVIEW

2026.02.05
アーティスト・小林繭乃と三平硝子によって生み出されるモンスターたち / 二人展「Monster:モンスター」出展インタビュー
-
SERIES

2026.02.04
90年代英国美術の革新を辿るテート美術館展から、映像の現在地を問う恵比寿映像祭まで。 / 編集部が今月、これに行きたい アート備忘録 2026年2月編
-
REPORT

2026.02.04
TOKYO ART BOOK FAIR 2025で1万円あったら何を買う? #2 服部恭平、田部井美奈、井上岳(GROUP)に聞いた



